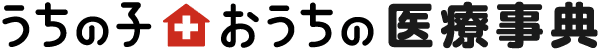しょくぶつちゅうどく 植物中毒 [猫]
概要
猫にとって毒性のある植物を食べてしまって起こる中毒です。
基礎知識
植物のなかには猫にとって毒性のあるものがたくさんあります。
種や根など部分的に有毒な植物もあれば、すべての部分が有毒な植物までさまざまです。
猫と人とでは体に入った有害物質を無毒化する機能のしくみが一部異なるため、人にとっては無害でも、猫では有害になる植物があります。
原因
毒性のある植物を摂取することで体に異常をきたします。
家の中の野菜や観葉植物、外に自生する野草や樹木など様々な植物が中毒の原因になることがあります。
野菜
ネギ、ニンニク、ニラ、ブドウ、レーズン、アボカドなど
観葉植物
ユリ※、アサガオ、アジサイ、シクラメン、ポインセチア、チューリップ、キキョウ、ボタン、ルピナス、ショウブ、ヒヤシンス、スイセン、スズラン、アイビーなど
※切り花の花瓶の水も有毒です。
野草・樹木
ツツジ、ソテツ、センダン、ゲッケイジュ、イチイ、キョウチクトウ、オシロイバナ、ドクウツギ、ドクゼリなど
症状
食べた植物の種類と量、食べてからの経過時間によりますが、これらの症状が出る可能性があり、命にかかわることもあります。
・嘔吐
・下痢・血便
・血尿
・よだれ、泡をふく
・震える、痙攣(けいれん)する
・元気がない
・ぐったりしている
・黄疸
・意識がなくなる
検査・診断
症状の経過から原因を推測し、問診により原因を推測していきます。
問診が最も重要になります。
食べた瞬間を見た場合以外は、中毒物質を摂取した可能性がないかを聴取し、そのほかの原因を除外して中毒疑いの診断をつけていきます。
同時に、血液検査やレントゲン検査、エコー検査などから全身状態を把握し、処置の判断をします。
全身状態や食べた植物の危険度によっては迅速な処置が必要になります。
治療
植物中毒の治療は以下のとおりです。
緊急処置
救命処置
意識がなく、命に関わる恐れがある場合は最優先に行います。
薬剤により吐かせる
食べた植物の種類と食べてからの経過時間によっては行いますが、食道粘膜などを傷つける恐れがないかを判断する必要があります。
全身麻酔下での胃洗浄
内視鏡や開腹などで行います。意識がない、吐かせられないくらい大量に食べた、胃粘膜からの吸収をすぐに止める必要があるなどの場合に行います。
内科治療
全身状態が安定していれば、内科的に治療をします。
内服薬
活性炭などで有毒物質を吸着させたり、下剤などで排出を促したり、胃粘膜保護や炎症を抑える薬などがあります。
点滴
全身の血液循環を促し、有毒物質を薄め、排出しやすくします。
これらの治療は有害物質を現状以上に吸収させないように止め、体から排出するための治療です。
肝障害や腎障害など中毒による障害が起きていれば、そのための適切な治療を実施する必要があります。
病院探しのポイント
・緊急治療が必要な場合があります。摂取の可能性や疑わしい症状があるときは至急診てもらえる病院を探しましょう。また、このような緊急事態に備えて、かかりつけのの病院の休診日や夜間診療をしている病院をあらかじめ調べておきましょう。
・複数回の通院や長期の入院が必要となる場合があるため、アクセスの良い病院だと通う際の負担が少なく済むでしょう。
予防
猫にとってどんな植物が毒性をもつのかを知っておくことが大切ですが、種類が非常に多く、すべてを把握することは困難です。そのため、野菜は毒性のあるものを把握しておき、観葉植物は基本的に毒性があるものとして扱いましょう。
その上で、それらが猫の口に届かないように置き場所を工夫して誤飲予防の対策をしましょう。
また、外の野草や樹木の葉などを食べる可能性もありますので、室内飼育を行いましょう。
タグ
部位
関連する病気

監修
アイペット損保 獣医師チーム
アイペット損害保険株式会社
獣医学科卒業後、動物病院にて小動物臨床に従事。現在はアイペット損保に勤務。
獣医師であり飼い主/ペット栄養管理士の資格取得
アイペット損保を通じて、飼い主さまがにワンちゃんネコちゃんと幸せに暮らすための情報をお伝えしていきたいと思っています。
アイペット損害保険株式会社